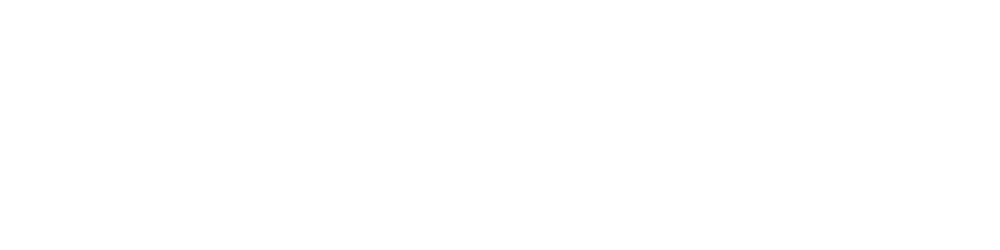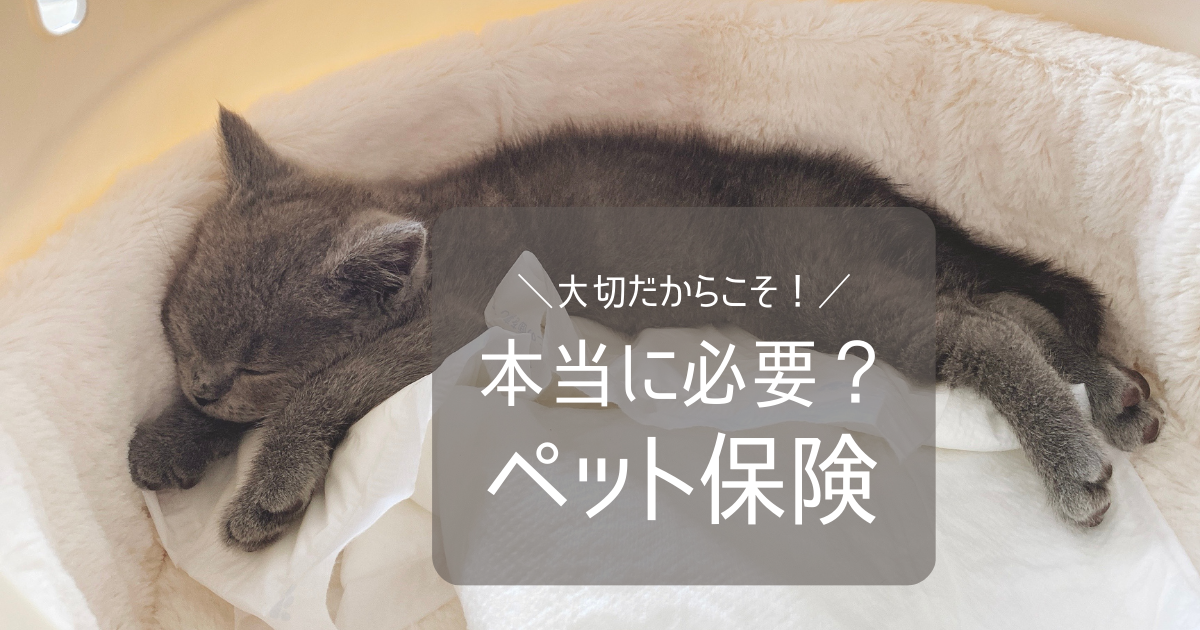「愛猫を守るために、ペット保険に入った方がいいのかな?」
猫をお迎えした直後、多くの飼い主さんが一度は悩むテーマではないでしょうか。
私も例外ではなく、ペット保険に加入していました。けれど、数年経って解約を決断。その理由や、私が実践している健康管理の工夫についてまとめました。
私がペット保険をやめた理由

ごまちゃんをお迎えしたとき、すぐにペット保険に加入。
最初は、「猫を家族として迎えるなら、保険に入るのは当然!」と思っていたんです。
でも数年生活してみると、保険を使う機会はほとんどなく、
「保険に払うお金より、自分で貯金や積立投資した方が効率的かも?」
と思うようになりました。
かかりつけの獣医さんにも相談してみると、
「病気になってしまった場合、保険に払う金額と病院に払う金額はトントンになることが多いですよ」
との一言。
この言葉で解約の決心がつきました。
保険に入っている安心感はあるけれど、現実的な数字を見てみると、自分で備える方が納得感がありました。
保険が必要か迷った理由
迷ったポイントはこちら。
- 急に大きな出費が必要になるかもしれない
→ 数百万円なら貯金から出せそう - 愛情の証としての保険
→ 保険に入ることで「猫を愛している証明」になる気がしたけれど、本当に大事なのは病気になったときにきちんと治療してあげること - 保険証の写真がかわいい
→ 確かにかわいい。でも、保険証でなくてもいいかも
さらに現実的なデメリットも。
- 多くの保険が50%や70%しかカバーされない
- 一部の疾患は対象外になる
- 健康でも年齢を重ねるごとに保険料がどんどん上がっていく
保険のメリット・デメリットを知ることが大事!
こうして整理してみると、保険に入る安心感よりも、自分で計画的に備えた方が納得感があるなと感じました。
今後の健康をどう守るか
これからも続けたいのは、 日々の小さな変化に気づくこと。
少しでも「いつもと違う」と感じたら、すぐに動物病院に相談するつもりです。
さらに、健康管理への意識も高まりました。
- 定期的な健康診断
- 食事やおやつの質をキープ
- 毎日の体調チェックや体重管理
など、保険がないからこそ、日々の健康管理を大切にしています。
そして「いざ」というときに迷わず支払えるように、家計の中で猫の医療費をしっかり優先順位に入れておくこと。
私は、ごまちゃん専用の積立(月1万円)をして備えています。
保険に入るのがおすすめなパターン
もちろん「ペット保険は絶対いらない!」というわけではありません。
以下のような場合は、むしろ加入をおすすめします。
- まだ貯金が少ない
- 病気のリスクが高い猫種を飼っている
また、病院にかかることが増えるシニア期になったら、そのタイミングで保険を検討しても良さそうです。
さらに、猫をお迎えしてすぐのタイミングで入るのもおすすめ。
というのも、病気が見つかってからだと新規加入できないことが多いからです。
おすすめのペット保険
もし加入するなら、評判の良いこちらを検討してみるのが安心。
- アニコム

- アイペット

通院・入院・手術まで幅広くカバー。
どちらも口コミやサポートの評判が良く、検討する価値ありです。
ごまちゃんが0歳〜2歳まで入っていたのはアニコムのペット保険で、受診時に窓口精算できたり健康診断の無料チケットが毎年もらえたり、正直、とてもいい保険だなと思いました。
自分に合った選択を
わが家は「健康管理+積立」でやっていくことにしましたが、ライフスタイルや猫ちゃんの性格・体質によってベストな選択は変わります。
大切なのは、「どんな備え方が自分に合うか」を考えること。
この記事が、ペット保険を見直すきっかけになれば嬉しいです。

子猫の時は、部屋の中の危険から守るためにケージがあると安心です。特に誤飲や骨折に注意!
▼こちらの記事もおすすめ